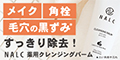記事は単純明快に
2020年6月9日
序章
記事の書き方は人それぞれで個性があってパターン化していたりします。人なりのスタイルをどうこうするのはとても難しいものです。
自分にとって素敵な文章が書ける方の記事が真似できるならば、誰しもそうしたいところでしょうけれど、最初は真似しても結局元の自分のスタイルに戻っってしまい自分のスタイルでしか記事を書くことはできません。
人のスタイルが真似できて記事が書けるって方は、それだけで既に相当な文筆力を持っているってことなのだと思います。
多くの人にとって良かれ悪しかれ自分の文筆スタイルというものが、これまでの生活習慣の中で既に出来上がっていると思うのです。この生活習慣とは考え方や学校での勉強の姿勢などから、時間をかけて少しずつ出来上がってきたものだと思います。
そのため長年かけて出来上がった生活習慣を変えるのが難しいように、大人になってしまった人の文章の書き方を変えるというのは、それこそ血の滲むような努力をしない限り不可能ではないでしょうか。 思い切って、文章作成講座的なものを受講してみるのも良いかもしれません…それ、お前が率先して受講せいって言われそう😅

読んでもらえる記事にするには
それでもどうにかして読んでもらえる記事を作りたいと思ったら、そこは記事の書き方を変えるしかないでしょう。これは記事の内容変えるというのではなくて書き方スタイルを変えるということです。
書き方スタイルを変えるって難しそうな気がしますけれど、要点さえわかればそんなに難しくないと思います。こんな風にわかったようなことを言っていますけれど、私自身も書き方スタイルについて思うところがあってこの記事を書いています。
まず私の記事の書き方は、一つの記事の中にたくさんの情報を押し込んでしまうことです。それもちゃんと整理もされていない情報を強引に詰め込んでしまうのです。
これは記事を読む人にとっても記事を読み終えるには忍耐が必要で、大変苦痛なことになってしまうでしょう。
それゆえに記事を読み終える苦痛な作業を続けてくれる人は、ほとんどいないと思った方が良いと思います。つまり記事をちらっと見て「あっ合わないな」と、読者は本能的にさっと去っていってしまう可能性が高くなります。
これでは何のために精魂込めて記事を書いているのかの、意味がなくなってしまいます。少しでも読んでもらえる文章を作るにはどうしたらよいか、自分なりに例を上げて考えてみたいと思います。
読みやすい記事にするために参考にする記事
読みやすい記事にするため 例として使用する記事は、静吉の記事が最も適切です。
静吉の記事の多くは先に言ったように、多分に内容を詰め込み過ぎています。
さらにその伝え方が幼稚で劣るので、記事の内容がより伝わりにくくなっています。そこで今回は、過去記事をもとにどのようにしたらよいのか考えてみることにしました。
実際にこのブログカードの記事に手を加えて、分かりやすく読みやすい記事づくりをしてみたいと思います。 i-shizukichi.hatenablog.com
例として取り上げた記事の分析
この記事の欠点は脈絡のない項目三点を、一つの記事の中に押し込んでいることです。この記事の内容は次の三点になります。
- はてなスター復活
- ブログアイコン変更と重要なこと
- ドア・オープナー
以上の記事を一つに記事にまとめて書いたことが、この記事の失敗の原因です。文章力のなさはちょっと脇に置いておきます。
この記事の失敗の原因を失敗と思わない方もいらっしゃるかもしれませんが、その考えは捨ててください。そのような考えを持つならば、明らかに私と同じように記事に内容の詰め込み過ぎで読みにくく感じられると思います。
この記事は明らかに脈絡のない記事の寄せ集めの失敗例と自分で思っています。なんたって書いているときに、関連性のないことを書き連ねてどうするんだって思っていましたもの。
最初から、一つ一つの記事を独立させれば、それだけで十分に一つの記事となり、とても分かりやすくかつ読みやすい内容で抑えられたと思います。もともとこのような記事にそれほど深い内容はないのです。
記事を書くというのは小説や文学を書くのではないのです。わかりやすく読みやすいというのも大事なポイントだと思います。与えすぎる情報はなにも残らないに等しいのです。
例として取り上げた記事を単純明快にする方法
例として取り上げた記事を単純明快にする方法は、すでに答えが出ていますね、お分かりですか。
そうです。
例として取り上げた記事を、3本のそれぞれ独立とした記事に仕上げれば良いのです。ということは一本の記事で3本の記事が作れるわけです。
一本の記事で3本の記事が作れたら、記事作成の上でもネタの温存ができて非常にありがたいとは思いませんか。
参考例としてこんな記事がありましたので紹介します。
この記事はツイッターから知ったのですが、この記事を読んで自分は失敗したなあって思いました。
なぜ失敗したと思ったかというと、記事の内容がドア・オープナーのことだけについて書いてあるからです。この記事は単純で、とても分かりやすい内容でした。これがブログ記事での成功の素だと思います。少なくとも静吉はそう思いました。
今の時代ブログ記事を読むのだって没頭して読んでいることなどはできません。
誰もがしたいことはいっぱいあるのです。
かなり以前から安近短というワードがありました。
ブログは安近短のセオリーに従って書くのは良いと思うのです。
一つの記事の中に別の記事を入れるのは、多分に興味を殺がれる原因になると思います。
それはなぜかというとその記事に興味を持って読み始めたのに、途中で違う記事の内容になってしまったら、もう良いやと思われてしまう可能性があります。
この記事の内容的なことは実際には私も書いてあるのですけれど、残念ながらはてなスター復活とブログアイコンの変更なんたらというタイトルで、どこにも焦点が定まらないで、記事全体が霞んだ感じがします。
静吉もドア・オープナーの記事を書くときに、この3本の内容はそれぞれ単独記事にしたら良いのではないかなと思ったのですけれど、単独記事を書くのが面倒臭かったので、3項目を一緒にした記事を書いてしまいました。
記事が書きたくてブログを書いているのに、面倒臭くて3本の記事を一つにしまうなんていうのは愚の骨頂とも言えます。このことは今では非常に反省事項です。
結論としては安近短で参考例の記事を再度書き直し
つまりは一本の記事を三本の別々の記事に仕上げるということです。
この試みをこの記事の中でやってしまっては、結果的に元の木阿弥になってしまうのでそれはしません。この記事では一本の記事を三本にする実験をするよってお知らせということになるわけです。
例として取り上げた記事を元に三本の記事とし、明日から一日一本公開していきます。記事内容そのものにはほとんど手は加えないつもりですので、参考までにざっと目を通していただけたら嬉しく思います。
そしてご自分の記事をご覧になって自分の記事の中にネタが詰め込みすぎてないか検討し、伝えたいことを単純明快にして分かりやすい記事を書くという作業をしてみると良いかなと思います。
今回は自分の過去記事を見直してリトライしてみようってことでリライトし、分かりやすい記事に書き直してみましょうってことをお伝えし、リライトにチャレンジが主題でした。
内容は実に単純なのに、相変わらずわかりにくい鈍(なまく)ら記事になりました😂
それではこの記事は静吉がお送りいたしました。
◇◇◇◇◇
Amazon.co.jpアソシエイト